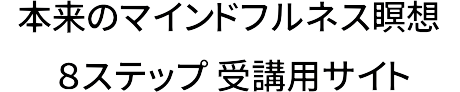基本の呼吸方法は腹式呼吸です。腹式呼吸で得られることは絶大です。
どの瞑想方法に取組むときも、格段の差ができます。ですから、最初の段階で基本として腹式呼吸の訓練をすることはとてもプラスになります。また、日常でも腹式呼吸になっていることは体の健康、心の安定や人生の安定にもつながります。
なお、ステップ2でできるだけできるようになっておくと良いですが、完ぺきにまでできるようになる必要はありません。瞑想の実践を進めていくにつれてできているようになっていきましょう。
胸式呼吸と腹式呼吸
呼吸のし方には、胸式呼吸と腹式呼吸があります。
胸式(きょうしき)呼吸は
胸を膨らませて行う呼吸法で、肋間筋(ろっかんきん)などの胸の周辺の筋肉を使います。
空気を吸い込むとき胸や首肩を動かすので、その周辺に力が加わります。肩が上下することが筋肉に緊張状態を与え喉が閉まるなどの影響もあります。そのため瞑想には不向きです。
腹式(ふくしき)呼吸は
肺の下にある横隔膜(おうかくまく)を使い横隔膜が上下に動くことで呼吸します。
呼吸によって胸の周辺の筋肉が動くことはあまりありませんから、首や肩、喉がリラックスした状態を保てます。重心も下にさがり体に安定感が生まれます。安定的な空気の供給も可能になります。
そして脳から直接出ている末梢神経は迷走神経と言い腹部にまで分布していますが、腹式呼吸は腹部までの迷走神経のバランスを調え、心身のリラックス効果があります。
そのため瞑想に適していますし、さらに癒しの効果があります。
また腸が動き腸の活動が良くなり、研究によって腸と脳の関係が解明されるようになってきていて、ストレス耐性や癒し、免疫力向上などに腸の重要性がわかってきています。
腹式呼吸の訓練法
坐ってする方法と寝た体勢でする方法がありますが、やり方を理解したら、坐ってするのは日常生活の中で少しの時間でもしましょう。また、寝た体勢は就寝時に寝床に横になったらすると、良い睡眠のためにもよいです。
- 体全体の力を抜いて仰向けに寝るか、坐って背筋を伸ばします。
- 腹部の動きを確認するためオヘソのあたりに軽く片手をのせ、胸が動いていないか確認するためもう片方の手を胸の上にのせます。腹式呼吸は腹部が息を吸ったとき膨らむ、吐いたとき縮む呼吸です。空気を吐き出すときも吸うときも動くのは腹部だけという点に注意します。
- オヘソの下、下腹部の中に意識を向け、中に空気袋があると心の中でイメージを持ちます。
- その空気袋が息を吸うと膨らみ、吐くと縮むのをイメージしながら何度か呼吸をしてみます。
- そして、口を少しすぼめ、ゆっくりと口で「スー」か「フー」と空気に音をつけるようにして息を吐きはじめ、10秒ほどかけてゆっくり腹部の空気袋が縮んでいくのを心の目で見ているようにして息を吐きます。
- 空気袋が縮みきり、もう吐き出せないくらいに空気を吐ききったら、次は鼻から空気をゆっくりと10秒くらいかけて吸い込みます。吸うときは鼻で吸い、腹部の空気袋が膨らんでいくのを心の目で見ています。
- 腹部が膨らみ、もう吸えないくらいに空気を吸いきったら5に戻ります。
- 5~7の繰り返しを3、4回位からはじめて、なれてきたら回数を増やします。
- そして回数を増やして何度か練習したら、息を吐くときも鼻から吐くようにします。
- 体全体をリラックスさせて取組みます。
息を吐く時も吸う時も動くのは腹部だけで、腹部以外はほとんど動かないようにすることが重要です。
寝た体勢でする場合は、体全体がリラックスできていてピタッと背中全体が床についているかも気にしましょう。もし床から離れているとしたら、力が入っている可能性がありますので呼吸とともに体をゆるめるようイメージします。