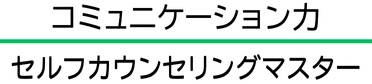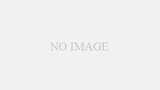― 人間関係の構造を理解する力を育てる
「なんでそんな言い方するの?」「どうして伝わらないんだろう…」「そんなつもりじゃなかったのに」、こうした人との「ズレ」や「誤解」に、心を悩ませたことはありませんか?
それは、誰かが悪い、あなたのせいというわけではなく、そもそも「人は違う世界を生きている」という前提があるからです。
このセッションでは、すれ違いや誤解の正体を構造的に理解し、人間関係の「ズレ」を冷静にとらえる力を育てます。
ズレや誤解が起きる「3つの構造」
1.認知の違い ~ 見ているものが違う
人は、同じ出来事でも「見ている視点」や「意味づけ」が異なります。
例:会議で発言が少ない人に対して
- Aさん:「あの人はやる気がない」
- Bさん:「意見を言うタイミングを探してるのかも」
脳は自分の「慣れたパターン」で現実を解釈するため、ズレが生まれるのです。
2.価値観の違い ~ 大切にしているものが違う
たとえば、次のように、人によって違う「正しさ」「優先順位」があります。
- 「時間に厳しい」対「 柔軟でいいじゃない」
- 「個人主義が自然」対「 協調第一が当たり前」
- 「本音を言うのが信頼」対「 空気を読むのが礼儀」
価値観がぶつかるとき、相手が「非常識」に見えてしまいます。
3.無意識の前提の違い ~「当たり前」が違う
人は誰でも、無意識に「これが普通」と思っていることがあります。でも、それは「自分の文化」でしかないことも多いのです。
- 「返事はすぐ返すべき」
- 「遅刻は失礼」
- 「ありがとうは必ず言うべき」
「当たり前」が違えば、すれ違いは当然起きます。
ズレや衝突は「関係の危機」ではなく「理解の入口」
誤解やズレが起きたときに大切なのは──「相手の意図や背景に関心を向ける姿勢」。
たとえば
- 「どうしてその言い方をしたのかな?」
- 「この人にとって、これはどういう意味だったんだろう?」
- 「どんな価値観がその反応を生んだのか?」
そう問いかけることが、対話の扉を開いていきます。

ズレに気づいた体験を振り返る
次の質問に答えてみてください。
- 最近、人と「なんとなくすれ違った」「誤解された」と感じた出来事はありますか? そのとき、あなたはどんな意味づけをしましたか? 相手には、どんな前提や価値観があったかもしれませんか?
- もしそのとき、冷静に「違い」を受けとめる視点が持てていたら、どう感じ方や行動は変わっていたと思いますか?
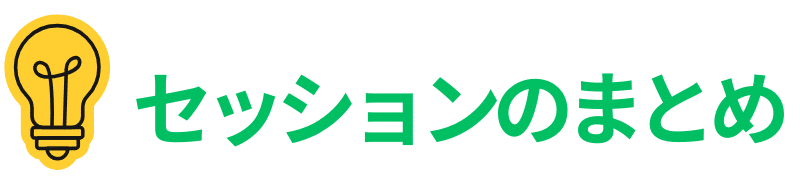
ズレや誤解は、関係を壊す「障害」ではなく、違いと出会い直す「チャンス」です。人は違って当たり前。その違いを「否定」ではなく「好奇心」で見るとき、対話の扉がふたたび開いていきます。
次のセッションは、ズレや衝突の場面で実際に使える、「誤解や対立を乗り越える対話技法」に進んでいきます。