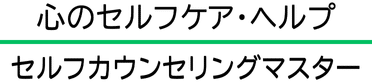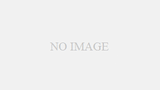なぜ、どうしてという言葉を意識せずに使っていたら、これからは注意してみましょう。
「なぜ」「どうして」の弊害
失敗やミスをしたり問題を起こしたとき、一般的に「なぜ?」「どうして?」と問うことをしますが、それは、多くの人は意識・無意識で非難されている、責められていると感じるため、心はマイナス状態になります。
子どもの頃から失敗やミスをすると、親、周囲の人に「なぜ、どうして、そんなことをしたの?!」と叱られたことから、自我の防御が働き、心の自由度は低くなります。
心の病気の原因になっていることも
鬱病などの心の病気も、過去や現在の出来事に対して「なぜ、どうして、あんなことを?」等と問うことが繰り返されてなります。
自分自身に「なぜ、どうして、そうした・しなかった?」等と自己批判することが繰り返されて、心が固くなってなります。

「なぜ」と「どうしたら」の違いを体感してみよう
- 自分のことでネガティブに思っている性格や出来事などを1つ書きます。
- それ見ながら「なぜ、どうして」と数分、考えます。どんなことを考えたり、どんな気持ちになってきたでしょう。
- 次に数分それを「どうしたら、次は・これからは良いだろう?」と思いながら見て考えます。
- どんなことを考えたり、どんな気持ちになってきたでしょう。「なぜ、どうして」とどう違うでしょう。違いを書いてみます。また、考えついたことがあったら書いてみます。
ネガティブな出来事は「どうしたら」と問う
過去・現在の失敗やミス、問題について「どうしたら、次は・これからは良いだろう?」と問えば、非難されている、責められているとは感じず心はマイナス状態にならずにすみます。
さらに、未来のプラスの可能性を認められ肯定されていると感じます。
そして、失敗やミス、問題を繰り返さないためにどうしたら良いかを前向きに考えられるようになり、心がマイナス状態になっている時よりも、広い視野で解決策を見つけることも可能になります。
より具体的な策を見つけるためには+して
より具体的な解決策、改善策を見つけようという場合は、「どうしたら、次は・これからは良いだろう?」にプラスして「良くなるためには何があれば良いだろう?」と問い、考えるようにします。
自己否定感が強くなっている場合
様々なことがあって日常的に自己否定感が強くなっている場合は、「どうしたら、次は・これからは良いだろう?」と問うても、そんなことは考えられないと自己否定感を持つことも考えられます。
しかし、そういうときも「なぜ、どうして」思考からは離れましょう。そして、少しずつ「どうしたら、これからは良いだろう?」と問うことをしていきましょう。