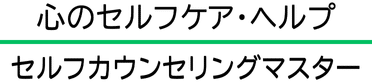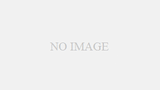私たちの心には、CP、NP、A、FC、ACという5つの自我状態が存在しています。
それぞれが本来持つ役割は大切ですが、もしどれかが極端に強くなりすぎたり、弱くなりすぎると
心のバランスが崩れ、 生きづらさや不自然な行動パターンが生まれてしまいます。
「自己一致」とは?
自己一致とは、心の中のすべての声を調和させながら、自然体の自分で生きることです。
- どの心の声も尊重し
- 必要に応じて使い分けられ
- 自分らしく、自由に、しなやかに生きる
それが、自己一致している状態です。
PACそれぞれの特徴と「健全な働き方」
CP(批判的な親)
- 健全な働き方::モラルや責任感を育む
- マイナスに偏ったとき:他人や自分を過剰に責めてしまう
- 調整のポイント:「正しさ」と同時に「思いやり」も大切にする。
NP(養育的な親)
- 健全な働き方:思いやりと支援を与える
- マイナスに偏ったとき:過保護・過干渉で相手を自立させない
- 調整のポイント:「支える」と「手放す」のバランスを意識する。
A(大人の心)
- 健全な働き方:現実を見て冷静に判断する
- マイナスに偏ったとき:感情を抑圧し、無機質になる
- 調整のポイント:「合理性」と「人間味」の両方を忘れない。
FC(自由な子ども)
- 健全な働き方:創造性と感情表現を発揮する
- マイナスに偏ったとき:衝動的・自己中心的になりやすい
- 調整のポイント:「自由さ」と「責任感」をバランスよく持つ。
AC(順応する子ども)
- 健全な働き方:協調性を発揮し、集団に適応する
- マイナスに偏ったとき:自己抑圧・自己否定に陥る
- 調整のポイント:「協調」と「自分の感情を尊重する」ことの両方を大事にする。
「バランスを取る」とは、すべてを活かすこと
PACそれぞれの自我状態は、あなたを豊かに、しなやかに生きさせるために存在しています。
- CPで責任感を持ち
- NPで思いやりを育み
- Aで冷静に現実を見つめ
- FCで喜びを感じ創造性を発揮し
- ACで周囲と調和する
すべての心を「否定せず、活かす」ことが、真のバランスです。
善いバランスを取れるようになるために必要なこと
1.自分の「偏り」に気づく
- どの心が強く出すぎているか?
- どの心が弱くなっているか?
まず、「気づく」ことが第一歩です。
2.A(大人の心)を育て、中心軸にする
バランスを整えるリーダー役は、A(大人の心)です。
- CP、NP、FC、ACのそれぞれを客観的に見守り
- 必要に応じて、行き過ぎた部分を緩めたり、弱い部分を育てたりする
Aの冷静で理性的な判断とあり方が、自我状態全体をプラスに育てていく軸になります。
3.弱い部分を「育てる」、強い部分は「緩める」
たとえば──
- FCが弱いなら「小さな楽しみを大切にする」ことから始める
- CPが強すぎるなら「完璧でなくてもいい」と意識する
4.逆のように振る舞う
マインナスにでている逆の自我状態のような振る舞い‣ありかた・言動をします。
たとえば──
- ACが強くなり自分を抑圧しすぎていたら、FCの自由な子どものように振る舞う
- 自分を批判するCPが高くなっていたら、NPの受容する思いやりのあるように振る舞う
5.「今、どの心で動いているか」を日常的に気づく
- イライラしているときは?
- 不安を感じたときは?
- 夢中になっているときは?
そのたびに、小さく気づくことで、無意識のパターンに飲まれずに、自分を整える力が育ちます。

私のバランスを見つめ直す
いつも自分の自我状態の状態を気づかうようにしましょう。
【 自分への問いかけ 】
- 「あなたの最近のそれぞれの自我状態はでうですか?」
- 「どうしたら良いと思いますか?」
【 ワークシート例 】
| 自我状態 | 最近は? | 調整ポイント |
|---|---|---|
| CP | マイナスに出すぎ | まあいいかとゆるめる練習 |
| NP | マイナスに出がち | 支えすぎず相手の力を信じる |
| A | 抑えがち | 冷静な事実整理の時間を取る |
| FC | 抑えがち | 1日1つ楽しいことをやる |
| AC | マイナスに出がち | 本音を伝える練習をする |

- バランスを取るとは、すべての心を活かして自然体で生きること
- そのためには、Aを中心に据えて、自我状態全体を育てていく
- 気づきと調整の積み重ねが、望まして自己一致への道になる