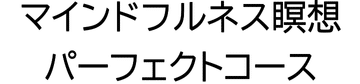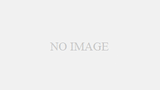仏教の基本的な立場、根本の教理は「縁起」です。そして次のように言います。
- 善因善果(ぜんいんぜんか)
- 悪因悪果(あくいんあくか)
- 自因自果(じいんじか)
善い行為をしたら善い果、悪い行為をしたら悪い果、そしてキリスト教で言うように自分のまいた種の果は自分が刈り取らなければならないということです。
そして、次のブッダの言葉があります。
ダンマパダ18
善いことをなす者は、この世で歓喜し来世でも歓喜し、ふたつのところで共に歓喜する。「わたしは善いことをしました」といって歓喜し、幸あるところにおもむいて、さらに喜ぶ。
善いことをするのはよぃことです。
では、どんなことが悪い行為・善い行為なのか。
行為の善悪の判断基準
まず、他者のこと・他者の行為に対して悪い行為だ・善い行為だと評価して表現してはいけません。この講義までに学びましたが、仏教を他者を評価裁定することに使ってはいけません。
仏教に限らず、例えばキリスト教でも人を裁くなで自分への自省が説かれていますが、教えはあくまでも自分をしっかりとするためのものであって、他者を評価したり裁くためのものではありません。
一般とは違うブッダの基準
一般的には、他者を「快」にするか「不快」にするかや、自分や他者の安穏をつくりだすか壊すかが善悪の基準と考えます。もっともな考えかたです。そしてそのように配慮するのも大切ですが、ブッダのいう善悪は違いがあります。善か悪かと判断をする軸が違います。
例えば、ブッダは釈迦国の一人息子の王子、跡継ぎでしたが息子が産まれると早々に出家しました。赤ん坊が産まれたからといってその子が無事に成長して跡をつげるとは限りませんからブッダの父親の王の安穏は破れ苦悩したでしょう。
さらに出家してブッダはまずサマタ瞑想を修行、そのあと苛酷な苦行をしましたが苦行は安穏な状態では全くありません。
また、ブッダは菩提樹の下で覚った後、その覚りを人々に説くことを躊躇しました。説けば人々は理解できず自分はわずらわしいめにあうと。つまり安穏が損なわれると。でも、その考えをかえて説きはじめした。
あとで後悔になるか・ならないか
次のブッダの言葉があります。
ダンマパダ17
悪いことをなす者は、この世で悔いに悩み来世でも悔いに悩み、ふたつのところで悔いに悩む。「わたしは悪いことをしました」と悔いに悩み、苦難のところにおもむいて、さらに悩む。
ダンマパダ67
もしも或る行為をなしたのちに、それを後悔して、顔に涙を流して泣きながら、その報いを受けるならば、その行為をしたことは善くない。
ダンマパダ68
もしも或る行為をなしたのちに、それを後悔しないで、嬉しく喜んで、その報いを受けるならば、その行為をしたことは善い。
ダンマパダの17には「悔いに悩み」、67と68は「後悔」するか・しないということが入っています。つまり行為をすること・しないこと、行為の内容がのちに後悔となるものか否かが、悪い行為か善い行為かの判断基準になります。
また、悔いる、悩む、後悔は自分の心がすること、自分の心の状態です。自分がしたことによる自分自身の心に現れる果です。つまり、善悪の判断の軸が自分軸です。
確かに何かをするときの選択は周囲へのその時の影響を考慮して、できる限り、周囲の人々、また自分自身のその時の安穏が壊れないようにすることが大事です。しかしながらそういう配慮もしつつという基準がブッダの説いている善悪にはあります。
後悔しないように今ここの選択をしましょう。
仏教、このプログラムは、自分に客観的に気づける力、メタ認知力を持ちますから、今ここの自分に気づくようになって、自分の心、自分が選択している・しようとしているのが、清い心からか、のちに後悔にならないかと考えるようにしましょう。
このステップ4から始まった気づきの力の開発は、今ここの自分に気づけるようになるためですが、ステップを進むにつけて力は強くなってきます。
悪い行為の種類
ダンマパダ69
愚かな者は、悪いことを行なっても、その報いの現れないあいだは、それを蜜のように思いなす。しかしその罪の報いの現われたときには、苦悩を受ける。
そして、仏教に「悪」は次のように種類が挙げられてもいます。
三悪行
身の悪行、語の悪行、意の悪行
十不善業道
殺生、偸盗、邪淫、妄語、両舌、悪口、綺語、そして貪瞋痴:貪欲、瞋恚、邪見
殺生から綺語までは意思による不善な行為・意思業で、貪瞋痴は心の不善な行為であり、不善根でもあります。殺生から綺語までは心の不善根の貪瞋痴によって生起します。
善い行為の種類
悪い行為と同様に身口意によることがあります。ブッダいろいろある善を6つにまとめて「六波羅蜜(ろくはらみつ)」として説いています。
六波羅蜜
布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧
六波羅蜜については次のページの講義で詳しく学べます。