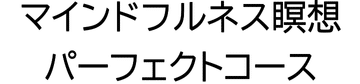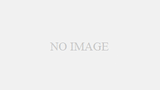参考に、日本の禅に関係した「軟酥(なんそ)の法」を紹介します。心身の癒しに効果がありますので、利用してみようと思ったら利用してみてください。
軟酥の法とは
軟酥(なんそ)の法は、日本の禅宗の臨済宗の白隠(はくいん)禅師が1757年に著わした『夜船閑話(やせんかんな)』に掲載されている心身を癒すイメージ療法です。
白隠禅師は、江戸中期の臨済宗の中興の祖と言われる禅僧で、下記のような達磨の絵を証が書き続けていたことでも知らています。臨済宗では坐禅をするときに白隠禅師がつくった白隠禅師坐禅和讃(はくいんぜんじざぜんわさん)を唱えます。
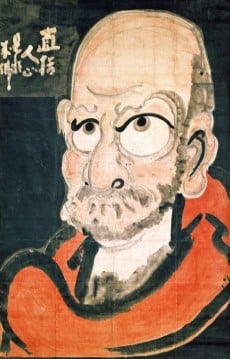
白隠禅師は26歳のころ、師僧の息道上人の看病と厳しく修行をしすぎたことで、今でいう神経症や心身症の状態の禅病となり肺結核も同時に患いました。
名医と言われる人も含めて様々な治療を受けて効果がありませんでしたが、京都の郊外に住んでいた白幽老人という人物に「内観法」と「軟酥の法」を教わり治癒しました。
手順・やり方
ヴィパッサナーの坐る瞑想のように坐るか寝た体勢になり手も同様とします。目は閉じましょう。
(なお、下記に掲載している原文の方法とは少し違うやり方になります)
- 鼻で静かに息をして、腹式呼吸をします。
- 頭の上に体に気持ちの良い精油がかたまったカタマリがのっているとイメージします。
- カタマリが体温でゆっくり溶け、温かく優しい精油が呼吸とともに頭のてっぺんからゆっくり頭全体を包むように流れていく、頭の中も優しく流れていくとイメージします。
- のど、首、両肩、両腕、両手、胸、お腹、背中、背骨、腰、おしりの表面・内部を流れていく、全身を流れていく、満たしていくとイメージします。
- 体の痛みや心のわだかまりなどがあったら、それらも流れていくとイメージします。
- そして、両足を流れ、足の裏に到達するまでイメージします。
これを幾度か繰り返します。
軟酥の法 原文
参考に原文も掲載しておきます。以下、『白隠禅師健康法と逸話』(直木公彦著/日本教文社刊)より引用させていただき紹介します。
予が曰く、酥(そ)を用ふるの法。得て聞いつべしや。幽が曰く、行者(ぎょうじや)定中(じょうちゅう)四大調和(じょうか)せず身心ともに労疲(ろうひ)する事を覚(かく)せば、心を起して応(まさ)に此の想を成すべし
譬へば色香(しきこうう)淸淨(しょうじょう)の軟酥(なんそ)鴨卵(おうらん)の大(おおい)さの如くなる者、頂上に頓在(とんざ)せんに、其の気味微妙(きみみみょう)にして、遍(あまね)く頭顱(ずろ)の間をうるほし、浸々(しんしん)として潤下(じゅんげ)し来(きた)って
両肩(りょうけん)及び双臂(そうひ)、両乳(りょうにゅう)胸膈(きょうかく)の間、肺肝(はいかん)腸胃(ちょうい)、脊梁(せきりよう)臀骨(とんこつ)次第(しだい)に沾注(せんちゅう)し將(も)ち去る
此の時に当たって、胸中の五積(しゃく)六聚(じゅ)、疝癖(せんぺき)塊痛(かいつう)、心に随って降下(こうげ)すること、水の下につくが如く、歴々として声あり、遍身(へんしん)を周流し、雙脚(そうきゃく)を温潤し、足心(そくしん)に至って即ち止む。
行者再びまさに此の観を成すべし。彼の浸々として潤下(じゅんげ)する所の余流(よりゅう)、積り湛(たた)へて暖めひたすこと。恰(あたか)も世の良医の種々妙香(めょうこう)の薬物(やくもつ)を集め、是れを煎湯(せんとう)して浴盤(よくばん)の中に盛り湛(たた)へて、我が臍輪(さいりん)以下を漬けひたすがごとし
此の観をなすとき、唯心(ゆいしん)所現(しょげん)のゆえに、鼻根(びこん)乍(たちま)ち希有(けう)の香気を聞き、身根俄(にわ)かに妙好(みょうこう)の軟蝕(なんしょく)を受く
身心調適(じょうじゃく)なること、二三十歳の時には遙かに勝(まさ)れり。此の時に当て、積聚(しゃくじゅ)を消融(しょうゆう)し腸胃(ちょうい)を調和(じょうか)し、覚えず肌膚(きふ)光沢(こうたく)を生ず
若(も)しそれ勤めて怠らずんば、何れの病(やまい)か治せざらん、何れの徳かつまらざん、何れの仙(せん)か成(じょう)ぜざる、何れの道か成ぜざる。其の功験(こうけん)の遅速(ちそく)は、行人の進修(しんしゅ)の精そに依(よ)るらくのみ