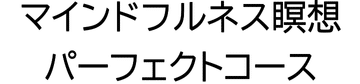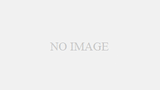慈悲の日常での実現は仏教ではということに限らず大事なことです。
そして、仏教に親しんでいると、自分は慈悲を理解できていて、それから外れることはしていないと思いがちになりますが、多くの場合、できてないものです。
なぜなら、ステップ3「慈悲とは」で学んだように慈悲は四無量心で、それはなかなか通常にはできるものではないからです。
多くの場合は、人間は無意識・無自覚に自分の好き・嫌い、快・不快で人を区別して対処しています。それでいて慈悲を大切にしていると思い込んでいます。
なので自分にしっかりと気づくことが重要になります。自分が感じていること、していることに気づかなければ、本当に慈悲ができているか・いないかに気がつくことはできませんから。そして、このことにヴィパッサナー瞑想によって養われる気づきが役立ちます。
四無量心を再掲します。
- 慈:あらゆる人に友愛の心、安楽を与えようという心を限りなく起こす
- 悲:あらゆる人の苦しみをなくしてあげたいという心を限りなく起こす
- 喜:あらゆる人の喜びを自分の喜びとして喜ぶ心を限りなく起こす
- 捨:あらゆる人に無条件で差別なく、かたよりなく、平静な心を限りなく起こす
慈悲、慈悲喜捨はすべて分け隔てなく「あらゆる人」です。捨でさらに「無条件で差別なく、偏りなく平静な心」です。
自分の好き嫌い、快・不快をもとに人を区別して対処していたら、慈悲としてはだめです。
このことを覚えておいて、日常にヴィパッサナー瞑想の気づきを活かして自分に気づき、必要があれば対処を修正して正しく慈悲を実践しましょう。