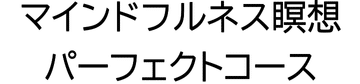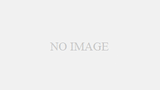これは取組まなくてかまいません。参考に紹介します。
経行(きんひん)は、坐禅を続けてするとき坐禅と坐禅の間にします。「禅の歩く瞑想」と講義名にあるように元は瞑想的なものでしたが、現在の経行は瞑想として取組むものではほぼなくなっています。
例えは臨済宗と黄檗(おうばく)宗のサイト「臨黄ネット」の説明も「坐禅のとき、睡気を防ぎ、足の疲れを休めるために行なう歩行運動。禅堂の周囲などを巡って歩く」こととなっています。
しかし元々の方法は瞑想的なものですので紹介します。
経行のやり方
曹洞宗の経行(きんひん)の正式なやり方は次になります。もし取組むときは、経行だけ単独でしてみてもいいですし、坐禅の後に続けて5分くらいしてみてください。
- 手は、後の講義の「禅の坐禅の関連作法」に説明のある叉手(しゃしゅ)をします。
- 姿勢はまっすぐにして、半眼で斜め前の下を見るようにします。
- 歩行は「一息半歩(いっそくはんぽ)」と言って、一呼吸の息を吐いて吸う間に、一歩を足の半分の長さ進めます。
- 息を吐きはじめ左足を上げ、その足を息を吸い終わるまでに足の裏の半分の長さだけ進め床に下ろします。左足の裏の真ん中が右足の親指の先と並ぶ位置になります。
- 次の吐く息で右足を上げ、その足を息を吸い終わるまでに足の裏の半分の長さだけ進め床に下ろします。右足の裏の真ん中が左足の親指の先と並ぶ位置になります。
- そうして、呼吸に合わせながら半歩半歩とゆっくりと歩みを進めます。吐くから吸うまでの一息と片足を上げて下ろすまでを合わせることがポイントです。
思考や感情や感覚が現れても、それにはとらわれないようにするのは坐禅と同じです。
禅の経行は坐禅堂など部屋の中を右回りに歩いていきますが、自宅でする場合などは、直線で歩いて隅まできたら方向転換して、また直線を歩くとしてかまいません。