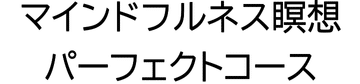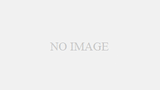ブッダは「人はなぜ苦しむことになるのか、どうしたら苦しまずにすむようになれるのか」の方法、真理を求めて出家しました。
そして、サマタ瞑想の修行や苦行をしたのち、ヴィパッサナー瞑想に取組んで、それを覚りました。その核心が『中道』『八正道』『四聖諦(ししょうたい)』です。
また、関連の三相(さんそう)の『諸行無常(しょぎょうむじょう)』『一切行苦(いっさいぎょうく)』『諸法非我(しょほうひが)があります。一切行苦は一切皆苦(かいく)、諸法非我は諸法無我とも言います。
仏教は、中道、八正道、四聖諦、三相を取組みによって理解する、智慧とすることが大事です。
中道‐八正道とは
ブッダが重視したのは人が苦しまずに済むようになることで、その方法・道が中道(ちゅうどう)。
中道は「ブッダが最初に説いたことと覚りの中身」の講義で紹介したダンマパダ以外にもダンマパダに書かれていています。20章「道」には次のように説かれています。
ダンマパダ273
もろもろの道のうちでは、八つの部分よりなる正しい道(八正道)が最もすぐれている。もろもろの真理のうちでは四つの句の四諦が最もすぐれている(後略)
八正道の詳細は、ステップ2で学びますが、ブッタの仏教の具体的な実践項目です。
仏教は「仏道」と言われることがありますが、それは仏教は哲学や思想というだけでなく実践が大事、具体的には八正道という実践が大事ということです。
ダンマパダ274
これこそ道である。真理を見るはたらきを清めるためには、この他に道は無い。汝らはこの道を実践せよ。これこそ悪魔をまよわして打ちひしぐものである
ダンマパダ275
汝らがこの道を行くならば、苦しみをなくすことができるだろう。棘(とげ)が肉に刺さったので矢を抜いて癒す方法を知って,わたくしは汝らにこの道を説いたのだ
ダンマパダ276
汝らはみずからつとめよ。もろもろの修行を完成した人は教えを説くだけである。心をおさめて、この道を歩む者どもは、悪魔の束縛から脱するであろう
そして三相について続きます。ブッダは次のように説いています。
三相とは
ダンマパダ277
一切の形成されたものは無常である(諸行無常)と明らかな智慧をもって観るときに、ひとは苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である
ダンマパダ278
一切の形成されたものは苦しみ(一切行苦。一切皆苦ともいう)と明らかな智慧をもって観るときに、ひとは苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である
ダンマパダ279
一切の事物は我ならざるものである(諸法非我、諸法無我ともいう)と明らかな智慧をもって観るときに、ひとは苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である
ブッダは、「形成された一切、全ては、諸行無常、一切行苦(皆苦)、諸法非我(無我)」と明らかな智慧をもって観られるようになりなさいと説いています。
どういうことかを解説すると
すべては無常 諸行無常
一切の形成されたものは無常であり
物質的に形成された物・出来事・現象のすべては無常=すべて変わる、消える、同じままあり続けるものはない、永続するものはない。
すべては非我 諸法非我
一切の事物は我ならざるものであり
すべての物事は無常、すべて変わる、消える、同じままあり続けるものではない、固定的・永続的な実体のものは何もない。現れて消える心身の現象の「私」「自分」等であり、すべて一時の現象にすぎない、「私」「他者」「私のもの」等々というものはない。
すべては苦 一切行苦
形成されたもの一切は苦ということはなかなか理解しにくいことですが、すべては無常にさらされているので「苦」は思い通りにならないという意味があります。
人間はこの肉体を生きる上で、次のような四苦八苦(しくはっく)を経験します。
まず、根本的な4つの苦
- 生苦:母胎の中にいられる安泰を捨てて、狭い産道を通り人間は生まれます。
- 老苦:老いていくことにより体力や気力などが衰退して思うようにならなくなります。
- 病苦: 様々な病気があり、痛みや苦しさに悩まされます。
- 死苦: のがれることのできない死に関する恐れ、不安、心配などの苦しみがあります。
そして
- 愛別離苦(あいべつりく):愛する人と生き別れ、死別する苦しみがあります。
- 怨憎会苦(おんぞうえく): 怨み憎んでいる人と出会う苦しみがあります。
- 求不得苦(ぐふとくく): 求めるものが思うように得られない苦しみがあります。
- 五蘊盛苦(ごうんじょうく):五蘊取蘊(ごうんしゅく)とも。五蘊(人間の肉体と精神)が思うがままにならない苦しみがあります。
また、仏教でいう苦は次の3種類で説かれます。
苦苦(くく)
一般的な心や体の苦しみのこと。四苦八苦など私たちは様々な心と体の苦しみを経験しながら生きます。
壊苦(えく)
生きていて、どんなに願っても、幸せ、快、楽が永遠に変化しないことはない、壊れるという変化・消滅による苦しみのことです。
行苦(ぎょうく)
心身の現象はすべて現われ消える、永続的ではなく一時的なもので、生きていることは心身の現象なので、生きることは、消える、永続はしない一時的ということにさらされ続けていて、思い通りにならない、満たされることはない苦であるという苦です。
四諦=四聖諦とは
四諦(したい)=四聖諦(ししょうたい)は「苦集滅道(くじゅうめつどう)」、苦諦(くたい)、集諦(しゅうたい)、滅諦(めったい)、道諦(どうたい)の4つです。
サンユッタ・ニカーヤ(『バラモン教典、原始仏典』長尾雅人責任編集より)には次のように書かれています。
まず、苦諦(くたい)は上記で説明した四苦八苦(しくはっく)が説かれています。
とうとい真実としての苦<苦諦>とはこれである。 つまり―
- 生まれることも苦であり、老いることも苦であり、病むことも苦である、
- 悲しみ・嘆き・苦しみ・憂い・悩みも苦である。
- 憎いものに会うのも苦であり、愛しいものと別れるのも苦である。
- 欲求するものを得られないのも苦である。
- 要するに、人生のすべてのもの‐それは執着をおこすもとである五種類のものの集まり<五取蘊>として存在するが、それがそのまま苦である。
そして
とうとい真実としての苦の生起の原因<集諦>とはこれである。つまり―
迷いの生涯を繰り返すもととなり、喜悦と欲望とを伴って、いたるところの対象に愛着する渇愛である。
すなわち情欲的快楽を求める渇愛と個体の存続を願う渇愛と権勢や繁栄を求める渇愛である。
とうとい真実としての苦の消滅<滅諦>とはこれである。つまり―
その渇愛をすっかり離れることである。すなわちそれの止滅である。それの棄捨であり、それの放棄であり、それから解放されることであり、それに対する執着を去ることである。
とうとい真実としての苦の消滅に進む道<道諦>とはこれである。つまり―
八項目から成るとうとい道(中略)である。
四聖諦それぞれと、そのつながり
四聖諦「苦集滅道」のそれぞれとつながりを簡単に説明すると次のようになります。
苦 諦
苦は三相で説明した通りです。一般的な苦しみという意味だけではなく「思い通りにならない」という意味、次の意味があります。
形成されたすべては、移り変わる無常、永続性のない固定的な実体はない非我・無我で、無常の縁起で成り立っている…、必ず変化してしまう、必ず消える…自分の思い通りにはならない…、一切行苦・皆苦、こういう苦の中で人間は生きている。
集 諦
こういう苦の中で生きているのに、変わらないと思い込んでいたり、変わらないでほしい、もっとこうあってほしい、嫌だ・好きだ、許せない、あのときこうすればよかった、あんなことをしなければよかった等々と心を乱す、欲をもち執着し煩悩を生じ、渇愛を生じる。
「私」「自分」「自分のもの」等々と心を乱す、欲をもち執着し煩悩を生じ、渇愛を生じる。だから苦しむことになる。
滅 諦
一切行苦・皆苦、諸行無常、諸法非我・無我、縁起を正しく理解できて得心できて、心を乱さず、欲をもたず、執着し煩悩を起こさないようになれば、そうなるようなことを発生させなくなれば、煩悩、渇愛を滅せば苦しむことにならない、苦しむことから解放される。
道 諦‐八正道
そして、心を乱すこと、欲をもつこと、執着すること、煩悩、渇愛を生じても対処できる、さらにそれらの発生を減らし・なくしていく実践の方法、一切行苦・皆苦、諸行無常、諸法非我・無我、縁起の智慧を得られる実践の方法、煩悩、渇愛を滅する実践の方法・道がある。
この実践の方法を実践していけば苦しむことにはならなくなる、苦しみから解放されて安楽に暮らせるようになる。この実践の道・ノウハウは八正道です。