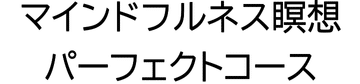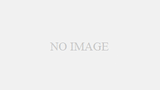【動画による講義】
【文字による講義】
慈悲の瞑想は、生きとし生けるもの、私、私の親しい人々、私の嫌いな人々、私を嫌っている人々を主語にして対象にした文章を唱えます。
このプログラムは、慈悲の瞑想に段階的に取組んでいきます。レベル1~4まで、唱える主語・対象を段階的に増やしてレベルを上げていきます。
段階的にレベルを上げる理由
理由は2つあります。
1つ目は、対象をはじめから多くして取組むと長い文章になり時間がかかり、今の段階でそうすると瞑想全体の取組みの負担が大きくなる心配があるからです。
2つ目は、慈悲の文章を唱えることに抵抗感を感じる場合があるからです。
慈悲的な文章を唱えること自体に抵抗感を感じる場合と、自分自身、自分が嫌っている人、自分を嫌っている人を対象に唱えることに抵抗感を感じる場合がありますが、抵抗感を強く感じながら取組むのは集中もしにくいですからおすすめしません。
ヴィパッサナー瞑想に取組んでいると脳の慈悲に関わる部位・機能が向上します。ですから、ステップを進みヴィパッサナー瞑想の取組みを進めていき唱える対象を増やすと、自然に抵抗なく効果的に習得していかれます。
慈悲の瞑想のやり方
前のページの講義で少し説明しましたが、坐る瞑想のように坐り、文章を心の中や声に出して唱えます。慈悲の瞑想はサマタ瞑想の一種です。文章と文章を唱えることに専念します。
1行1行、文を集中して唱えます。文章の内容を意識的に想像や考えたりする必要はありません。集中して唱えれば意識は文章の内容をしっかりととらえています。
なお、唱えて抵抗感を感じる場合は、言葉の意味は気にしないようにして、ただの呪文のように唱えるとよいです。
レベル1のやり方
そして、このステップのレベル1は次のようにします。
唱える主語・対象
主語にして唱える対象はレベル1は「生きとし生けるもの」とします。そうする理由は、これは具体的に対象を連想することが少なく心理的影響が少ないからです。
そして、前のページの講義で紹介したゴエンカ式やチャンミェ・サヤドーの文章が「生きとし生けるもの」と同様の「すべての生命」「すべの生きもの」を対象にした文だけであるように、「生きとし生けるもの」が主語の文が慈悲の瞑想の核心だからです。
核心の部分だけまず取組むことで、慈悲の瞑想の取組みに慣れることができますし、時間がないときなどは慈悲の瞑想はこの部分だけで取組むことでよいです。
唱える文章
前ページの講義で紹介した文を、さらにブッダが慈悲の瞑想について語った四無量心(しむりょうしん)の意味にした文です。四無量心は「慈悲とは」の講義で説明しています。
- 生きとし生けるものが幸せでありますように
- 生きとし生けるものが苦しみから解放されますように
- 生きとし生けるものが喜びに満たされますように
- 生きとし生けるものが差別やかたよりがなく平静な心でいられますように
(以上を1回)
- 生きとし生けるものが幸せでありますように
(3回繰り返す)
慈悲の瞑想に取組むタイミング
取組みたくなったときに慈悲の瞑想だけで取組む。または何か坐る瞑想をするとき、その瞑想の瞑想状態に入る前にする。特に朝一番の瞑想のときなど一日一度は慈悲の瞑想はしたいものです。
坐る瞑想と一緒に取組む場合は次のようにします。
- 坐る瞑想で姿勢を整えるところ左右揺振までします。
- 慈悲の瞑想をします。
- それから、坐る瞑想の瞑想状態に入ります。
- 最後に「生きとし生けるものが幸せでありますように」と3回唱えて瞑想を終わります。