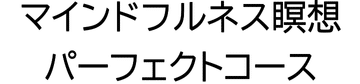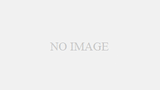【動画による講義】
【文字による講義】
手動瞑想は、日常生活の中で手軽に取組めて気づきの力を開発しやすいです。取組んでみましょう。
タイのルアンポー・ティアン・チッタスポー師が考案したものです。
ルアンポー・ティアン師は、2014年に亡くなったタイ仏教を代表する高僧のルアンポー・カムキエン師の師僧でその法脈の祖に当たる人で、珍しい経歴の高僧です。
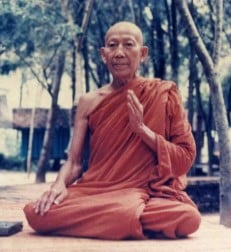
1919年、タイのルーイ県チエンカーン市のブホムという村に生まれ、はじめは13歳のとき、それから幾度か短期の出家をしながら、在家者として仏道の五戒を守り瞑想実践を継続し、46歳になろうとするときにいよいよ自分を変えなければならないと思います。
自分の心の中にまだ怒りの感情がある、自分の心はまだ苦(ドッガ)に束縛されている、この束縛に終止符を打つべきだと考えたと知られています。そして家を去りワット・ラングシムクダラムという寺へ行きました。
そこでルアンポー・ティアン師はただ自分の心と身体に気づいている瞑想実践をして、数日後に完全なる苦の消滅に達する大悟に到ったと言われています。
そして、ルアンポー・ティアン師は僧院を去り家に戻り、在家の瞑想指導者として3年ほど瞑想を教え法を伝えました。在家でいるより比丘という立場のほうがより多くの人に伝えられるだろうと1960年に再出家をし1988年に亡くなるまで瞑想と法を伝えました。
気づきの開発の瞑想
ルアンポー・ティアン師が教えた瞑想法はチャルーン・サティ(気づきの開発)と呼ばれています。師が亡くなってからもタイの東北地方を中心に約140の寺院で実践されています。
そして、チャルーン・サティには、ヨックムー・サーンチャンワという座って行う瞑想と、ドゥーンチョンクロムという歩いて行う瞑想があり、座って行う瞑想が手動瞑想になります。
手動瞑想のやり方
できれば姿勢をよくして座ります。椅子やソファに足は組まずに座ってでもかまいません。坐る瞑想の坐りかたをできるときはそれでいいです。
目は開けたままでいいです。気が散るという場合には半眼か軽く閉じます。そして、周りに視線を向けずにまっすぐ前を向いたまま手を動かします。
手の動かし方のポイント
- 両手を軽く指を伸ばして間は軽く閉じ、体の力をぬいてリラックスして動かしていきます。
- 手に意識を向けて、手と、手と腕の動きに気づきを切らさないようにして動かします。
- 動かす速さは普通にと説明される場合もありますが、ゆっくりめにして動きの一つずつをしっかり気づくようにしてすると効果的です。ルアンポー・ティアン師の動画ではゆっくりとした動きになっています。
- 大切なことは正しく手を動かすということよりも、しっかりと気づくことにあります。しっかり気づきがなければただの手の体操になってしまいます。
手を動かす手順
両手の指を伸ばして間は軽く閉じて、まず、左右の手をそれぞれ左右のももの上にふせて置きます。
- 右手を、小指側を下にして、ももの上に立てます。
- 右腕をまげ、右手を垂直に右肩の前のあたりの空間まで上げます。
- 右手の手のひらを、丹田=オヘソの下の右側へもっていきます。
- 左手を、小指側を下にして、ももの上に立てます。
- 左腕をまげ、左手を垂直に左肩の前のあたりの空間まで上げます。
- 左手の手のひらを、丹田=オヘソの下の左側へもっていきます。
- 右手を、手のひらを体にそわせて胸の真ん中に移動させます。
- 右腕を90度水平に開き、右手を右肩の前まで移動させます。※上記2と同じ位置
- 右手を、上記1のようにももの上に降ろし、手のひらをももの上にふせます。
- 左手を、手のひらを体にそわせて胸の真ん中に移動させます。
- 左腕を90度水平に開き、左手を左肩の前まで移動させます。※上記5と同じ位置
- 左手を、上記4のようにももの上に降ろし、手のひらをももの上にふせます。
- これが1サイクルで、このサイクルを繰り返します。
一つひとつの動きをしっかり区切って、動かしている手と腕とその動きをしっかり細かく気づくようにして動かします。
一つの動作をしたら一瞬そこで止め、しっかり心の中で止まっている状態にも気づいてから、次の動きへ移るようにします。
こうしていて、記憶や思考や感情、快や不快、痛みやかゆみなどが現れたときは、現れたとだけ気づいて、それに関して反応したり考えたりなどはせず、手への気づきを続けます。
参考動画
下記のカンポン・トーンブンヌムさんの動画をぜひご覧ください。
カンポンさんは、24歳の時の水難事故で全身麻痺の障害を負って16年間の失意のどん底を味わい瞑想に出会って苦しまずに生ききった人です。
手動瞑想をなさっているシーンもありますし、貴重な学びにとてもなります。